京都の北区に位置する今宮神社。その参道にあぶり餅かざりやがあります。
名物あぶり餅を、京都らしい風情のある店構えでいただくと、素朴ながら滋味深いお味にしみじみと歴史のあるお菓子の素晴らしさを感じます。

ここの創業は、江戸時代の寛永14年(1637年)で、当時の製法を今も守り続けています。
あぶり餅は、親指サイズのお餅を竹串に刺し、きな粉をまぶして紀州備長炭で香ばしく炙った後、京都の白みそをベースにした秘伝のタレにつけて仕上げられます。
焦げ目が付くくらい炙ったお餅の香ばしさに、白みそのタレの甘さが絡んでとても美味しいです。
なお、かざりやの向かいも、あぶり餅のお店で、一和(一文字屋和輔)といい、こちらは平安時代の長保2年(1000年)創業。なんと1000年以上の歴史があるお店で、日本で一番古い和菓子店といわれています。
かざりやも一和も、店構えは情緒あふれる京都らしい雰囲気で、お店の女性方が炭で餅を炙る姿には、京都の伝統と歴史を感じます。奇数が縁起が良いとされていることから、13本入りで提供されています。(一和は11本入りらしいです)
3人前からお持ち帰りもできますが、お店で炙りたてをいただくのが一番おいしいと思います。
ところで、かざりやも一和も、今宮神社の参道で、参詣客にあぶり餅を出してきたお店ですので、今宮神社についても書かせていただきます。
今宮神社のある場所には、平安京が出来る前から、疫神を祀る社があったといわれています。
平安京が出来てからは、都市として大きくなっていく一方、度々発生する疫病や災厄に悩まされるようになります。これを鎮めるための祭礼・祈祷が各地で盛んに行われましたが、そのひとつとして、正暦5年(994年)に、この地に祀る疫神に悪疫退散を祈る祭礼が行われました。長保3年(1001年)にも、疫神を鎮め祀るため再び祭礼を行い、このとき新たに設けられた神殿と合わせて今宮社と名づけられて、これが今宮神社のはじまりとなっています。
なお、今宮神社は「玉の輿神社」とも呼ばれています。その由来はこうです。西陣の八百屋の娘であった玉は、関白家の鷹司孝子に仕えていましたが、孝子が徳川三代将軍・家光に嫁いだ為、孝子に付き従って江戸城に入ります。そこで働くうちに春日の局(家光の乳母)に認められて家光の側室となり、後に五代将軍・綱吉の母・桂昌院となりました。八百屋の娘が将軍の側室になるなんて、すごいことですね。桂昌院は、西陣の鎮守である今宮神社が、当時荒れているのを嘆き、社殿を造営し、神領を寄進して復興に尽力したことから、このように呼ばれるようになったということです。
あぶり餅 本家・根元 かざりや
京都市北区紫野今宮町96(今宮神社東門南側)
HP(京都市)
あぶり餅 本家・根元 かざりや|【京都市公式】京都観光Navi
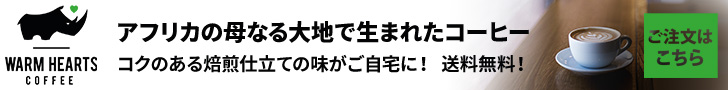


コメント